なぜこの掛け算が必要なのか?
青い海に浮かぶ小さな島。そこに集う保護された犬や猫たち。そして、その活動を支える企業のロゴ。この光景が現実になる日は、そう遠くないかもしれません。
環境省の最新統計によると、2022年度に日本では犬猫合わせて約2,434頭の犬が殺処分されています。これは10年前の38,477頭と比べると10分の1以下に減少していますが、いまだ1日に平均6頭以上の犬が殺処分されている現状があります。2023年度の統計では犬猫あわせて44,576頭が保健所などに引き取られており、多くの保護団体は「資金不足やボランティア不足に悩まされており、『保護ビジネス』との批判に晒されることもある」状況です。
世界に目を向けると、フランスやニューヨーク州などではペットショップでの犬や猫の販売禁止措置が決定されていますが、「日本では、ペットショップなどの生体販売により多くの犬猫が販売されている」のが現状です。欧州諸国と比較すると、日本の動物保護政策には大きな遅れがあります。
一方、企業は社会貢献活動(CSR)やサステナビリティを模索しつつも、具体的な成果や継続性に課題を感じています。「企業は利益だけを目的とした経営ではなく、社会的な責任を果たすことや持続可能なビジネスの実現が重要な経営課題」となっています。
日本列島には6,852の島があり、このうち本土5島(北海道、本州、四国、九州、沖縄本島)を除いた6,847の離島のうち、人が住む島は約416島とされています。その他の島々は無人島となっており、活用されていない自然資源が多く存在しています。
こうした課題や状況を俯瞰すると、「保護猫・保護犬×企業ブランディング×無人島」という掛け合わせには、社会課題と未活用資源を結びつける大きな可能性が見えてきます。今回は、この新しい事業アイデアの可能性を掘り下げていきます。
この組み合わせに気づいたきっかけ
波の音が心地よい夏の終わり、私は長崎県の小さな「猫島」を訪れていました。島に暮らす猫たちが陽だまりでくつろぐ姿、観光客が猫たちに優しく手を差し伸べる光景。そこには不思議な調和がありました。
人間よりも猫の数が多いその島で、観光客が猫と触れ合い、餌を与え、共存する様子を目の当たりにしたとき、ふと思ったのです。「自然に生きる動物たちの姿が、人々に癒しを与えている」と。
帰りの船の中で、スマートフォンをスクロールしていると、ある記事が目に飛び込んできました。ある企業のCSR担当者のインタビュー記事です。「一過性のイベントで終わってしまう社会貢献活動に、何か継続性と実感を持たせたい」という悩みが綴られていました。
そして、その夜。ホテルのベッドに横たわりながら、その二つの記憶が重なり合いました。島の猫たちと、継続的な社会貢献を求める企業。そこに「企業がスポンサーとなり、保護動物のための島を作れないだろうか?」というアイデアが生まれたのです。
さらに考えを巡らせていると、日本には多くの無人島が存在することも思い出しました。活用されないままの島々と、行き場のない保護動物たち、そして意義ある社会貢献の場を求める企業。これらを繋げば、新たな価値が生まれるのではないか——。
朝日が昇る頃には、「保護猫・保護犬×企業ブランディング×無人島」という掛け合わせのビジョンが、はっきりと見えていました。
なぜ相性がいいのか?
この三つの要素が交わるとき、そこには驚くべき相乗効果が生まれます。
まず、保護猫・保護犬にとって無人島という環境は、コンクリートの檻に囲まれた従来の保護施設とは比べものにならない生活空間を提供します。海風を感じ、土を踏み、自然の中で自由に動き回れる環境は、動物たちのストレスを軽減し、本来の行動パターンを取り戻す助けになります。島という限られた空間であれば、逃走や事故のリスクを最小限に抑えながらも、十分な活動範囲を確保できるのです。
企業側に目を向けると、「企業の島」という発想には強力なブランディング効果があります。「動物保護活動に貢献している」とPRすることは「企業イメージの向上や他社との差別化に繋がる」だけでなく、「今後のペット産業においても重要な戦略のひとつ」となります。特に、具体的な「場所」を持つことで、社会貢献の「見える化」が実現し、社員や顧客が実際に訪れて体験できる接点が生まれます。
現代社会において「近年、消費者は環境に配慮し、社会的責任を果たす企業に対して信頼を寄せる傾向があります」。SDGsへの貢献を目に見える形で示すことは、企業価値の向上に直結するでしょう。また、社員が保護動物のケアに参加することで「モチベーション向上や企業への愛着を高める効果」も期待できます。
無人島という存在も、この組み合わせに独自の価値をもたらします。使われていない島に新たな命を吹き込むことで、地域経済への貢献も生まれます。島という閉じた環境は、訪問者と動物たちの安全を確保しやすく、運営管理の効率化にも繋がるでしょう。
自然・動物・人間の新たな共存モデルとして、この掛け合わせには大きな可能性が秘められています。
ターゲット・価値提供・利用シーン
主なターゲット
- 社会貢献型のブランディングを求める企業(特にCSR/サステナビリティに力を入れる企業)
- 動物愛護に関心の高い個人や家族
- 独自の体験を求める観光客
- 環境教育の場を探している学校や団体
- エシカル消費に関心のある消費者
価値提供
- 企業:具体的な社会貢献の「場」とブランド発信機会、「長期的な経営や成長を目指す」上での差別化要素
- 保護動物:より自然に近い環境での生活、「一日だけの保護犬・猫の譲渡会やホームページでは里子にする決心のつかない里親候補たち」が「何回でも会いに来て里子を決められる」場所の提供
- 訪問者:普通の観光では得られない体験と社会貢献の実感
- 地域:新たな観光資源と雇用創出
利用シーン
企業は島をスポンサードし、社名を冠した「○○アイランド」として命名権を得ます。「自社SNSや広報誌での紹介」を通じて企業イメージを高められます。従業員の研修や福利厚生として島を訪問できるプログラムも提供し、「従業員が動物保護活動に参加する機会」を創出します。
一般観光客は入島料を支払い、動物と触れ合いながら、餌やりなどのボランティア活動に参加できます。
収益モデルとしては、入島料、企業スポンサーシップ(「パートナー」として参加)、島内での物販(オリジナルグッズなど)、ふるさと納税の返礼品などが考えられます。
課題と乗り越え方
最大の課題は、無人島の購入資金と初期整備費用です。「現在、すべての運営費・管理費は民間からの自費で支えられており、企業の協賛が必要不可欠」という保護活動の現状を考えると、資金調達が最重要課題です。
対策としては、クラウドファンディングと企業スポンサーの組み合わせで資金調達を行います。「保護団体は資金不足やボランティア不足に悩まされて」いるため、複数企業によるコンソーシアム形式で島の共同所有という選択肢も有効です。
また、動物の健康管理や島の環境保全に関しては、獣医師や環境専門家との連携が不可欠です。常駐スタッフの確保や遠隔医療システムの導入で対応します。現状「動物保護活動を行う団体は、資金不足やボランティア不足に悩まされており」、運営面での課題も大きいため、企業の人的・技術的リソースの活用も検討します。
アクセスの問題については、定期船の運航と宿泊施設の整備が必要です。初期段階ではデイトリップのみとし、徐々に宿泊施設を拡充する段階的アプローチを取ります。
社会的な理解を得るためには、「保護ビジネス」との批判を避けるために透明性の高い運営と情報公開を徹底します。動物福祉の専門家の監修を受けることで、科学的根拠に基づいた環境づくりを行います。
応用展開・派生アイデア
このコンセプトは様々な方向に発展可能です:
- 特定の絶滅危惧種保護に特化した島
- 企業の研修・リトリート施設を併設した島 – 「従業員のモチベーション向上や企業への愛着を高める効果」が期待できます
- 動物と共に暮らす短期移住プログラム
- 動物介在療法(アニマルセラピー)施設としての活用
- ドキュメンタリー制作やライブ配信による収益化 – 「企業は自社のメディアやSNSを通じて動物愛護に関する情報を発信」できます
- アプリ連携 – 「AnimaPick」のような「企業が保護活動を支援できるプラットフォーム」と連携し、「『パートナー』になり、保護活動を支援する」仕組みを構築
- 「譲渡会の会場を提供」する場としての活用 – 「一日だけの保護犬・猫の譲渡会やホームページでは里子にする決心のつかない里親候補たちも、何回でも会いに来て里子を決められる民家風の犬・猫サロン」としての機能
スモールスタートとしては、すでに存在する猫島とのパートナーシップから始め、企業スポンサーとのマッチングを行うことも考えられます。また「企業ができることとしては行政や民間の動物愛護団体の譲渡会に理解を示し、場所の提供を行う」という小規模な取り組みからスタートすることも有効です。
市場規模・数値シミュレーション
日本のペット関連市場は約1.5兆円規模であり、動物愛護への関心も高まっています。企業のCSR予算は大手企業で平均して売上の0.1%程度とされ、上場企業全体で推計すると約5,000億円の市場となります。「環境問題への配慮などを取り入れ、持続的に活動を行うことは企業としての評価を高め、信頼性を向上させる」ことから、この市場は今後も拡大が見込まれます。
また、「動物愛護への参加をビジネスメリットにも繋げる仕組みづくり」は「今後の重要な方向性の一つ」と考えられています。こうした背景から、本事業の市場ポテンシャルは大きいと言えるでしょう。
試算例
- 無人島購入費:1億円
- 初期整備費:1億円
- 収入:
- 企業スポンサー(1口10万円×100口):年間1,000万円
- 入島料(1人3,000円×月間1,000人×12ヶ月):3,600万円
なお、「企業が動物保護活動に参加する」ことで得られる「企業イメージの向上や他社との差別化」という無形の価値も大きいと考えられます。これは数値化しにくいものの、長期的な企業価値向上に貢献するでしょう。
先進事例から学ぶ
既存の動物保護と企業活動の連携事例からも学びを得ることができます。
パナソニックでは、家電製品「ジアイーノ」のブランディングと連携させ、保護犬猫の譲渡会を積極的に開催しています。「いまはまだ私の個人的な想いだけれども、いつか『会社としてのアクション』につなげられないだろうか」という担当者の思いから始まったこの取り組みは、企業イメージ向上と社会貢献を両立させています。
また、保護犬カフェSORAと明幸薬品株式会社の連携事例では、保護犬カフェと製薬会社が連携し、保護犬の紹介を通じて双方の認知度向上を図っています。
こうした事例からも、企業が「単なる慈善活動としてではなく、自社の経営理念や事業内容と結びつけながら、長期的な視点で動物愛護に取り組むことが、社会からの信頼を得て持続的な成長に繋がる道」であることが理解できます。
終わりに
波打ち際に立ち、島に暮らす元保護犬が嬉しそうに駆け回る姿を想像してみてください。その一匹一匹には、過去に人間に見捨てられた悲しい歴史があるかもしれません。しかし今、彼らは美しい自然に囲まれ、訪れる人々に癒しを与える存在になっています。その島を支える企業ロゴが、穏やかな海風になびくフラッグに描かれています。
これは単なる夢物語ではありません。「動物愛護は、現代社会における重要な課題であり、企業にとってCSR、サステナビリティ、そしてブランディング戦略において無視できない要素」となっています。ここに無人島という未活用資源を組み合わせることで、新たな社会的価値が生まれるのです。
従来の保護活動の枠を超え、「企業と動物愛護団体とのより一層の連携強化、消費者の動物福祉への意識向上」を促進するモデルとして、このアイデアには大きな可能性があります。自然の力、動物の命、企業の資源、人々の善意—これらが交わることで、私たちの社会に新たな調和が生まれるでしょう。
皆さんの身の回りにも、眠っている資源や可能性はありませんか?異なる要素を掛け合わせることで、全く新しい価値が生まれることがあります。あなたの企業や団体では、どのような社会貢献と組み合わせられるでしょうか?
次回は「古民家×テクノロジー×健康産業」という切り口で、新たなビジネスの可能性を探っていきます。どうぞお楽しみに。
関連リンク
- 環境省「犬・猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに処分の状況」
- 公益財団法人動物環境・福祉協会Eva「犬猫の引取り数と殺処分数」
- 離島経済新聞社「1ページで分かる離島経済新聞社」
- AnimaPick「企業向け動物保護活動支援プログラム」
- ELEMINIST「サステナビリティと企業ブランディング そのメリットや成功事例を紹介」
- セブン&アイ・ホールディングス「サステナビリティとは | 企業が取り組むメリット、ポイントを解説」
- Make New Magazine「パナソニックが保護犬猫の譲渡会?『個人の想い×社会課題』で『ジアイーノ』のブランディングに挑む」
- Readyfor「保護犬・猫とみんなの居場所」成功例をつくり全国の団体と連携したい
- 明幸薬品株式会社「保護犬カフェSORAさんコラボ!わんちゃん紹介!」
- 東北大学経済学研究科「CSRとしての動物愛護」
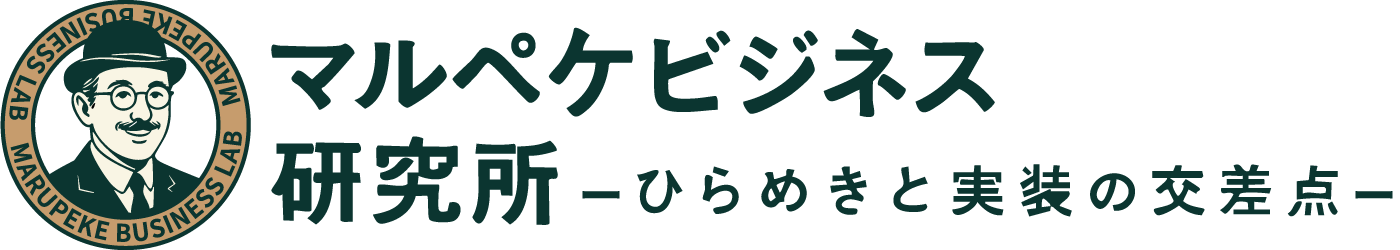

コメント